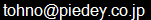|
||||||
|
(前編より続く) 100M級デストロイヤーは小さな船だ。パイロット控え室から数歩で既に格納庫の2階部分のテラスに出た。 2機の戦闘機が格納庫内に垂直に置かれていた。 手前に腹を見せて立っているのが、現在オルランド最強の制式戦闘機とされるMARK-IVファイターだった。 その脇では、オルランドでも屈指の戦闘機パイロットとされるミハイロフ・オオハラ中佐が整備員と何か話し込んでいた。 マイネは、敬礼して挨拶すべきだろうかと思った。 だが、オオハラ中佐はすぐにマイネに気付き、微笑んでウィンクした。「気楽にね。無理に気負うと逆に何もできなくなるよ」 マイネは、少し緊張がほぐれた気がした。この人が相手なら安心して戦えるという気がした。 だから、すぐ微笑んで答えた。 「はい。ありがとうございます!」 マイネは格納庫の奥に進んだ。 そこに、背中をこちらむ向けて立っているのが、マイネが乗る予定の機体だった。 中央部の背中の左右上方に向けて、2つの角張ったノズルが付いていた。これまでのオルランドの戦闘機には存在しなかったものだ。 高機動可変ベクトル推進ノズル……。 腹側にももう1つ付いているので、合計3つだ。 それ以外は、オオハラ中佐のMARK-IVファイターとそっくりだった。だが、これは最新型のMARK-IVファイターではなく、MARK-Iファイターなのだ。同じサイズに納めるために似た外見になっているが、全く別個の機体なのだ。 つまり、マイネが乗るのは、高機動可変ベクトル推進ノズルが付いた旧型機ということになる。 マイネの機体の前には、気心の知れた整備兵達が待っていた。 「機体は完璧です」と彼らは胸を張った。 マイネを礼を言い、そして腹側に引き出された座席に座ってベルトを締めた。整備員が集まってベルトを調整してくれた。 「濡れていますか?」と整備員の一人が言った。 マイネは恥ずかしくなりながらも答えた。 「はい……」 整備員はマイネのパイロットスーツの股間の部分のジッパーを引き下ろし、生身のマイネの秘所を明るいライトの下に晒した。そこは確かに何かのねっとりとした液体で濡れていた。 整備員はシートの脇のスイッチを操作した。座席の下から、男根に似た形の装備がせり上がってきた。 「よろしいですか?」と整備員は言った。 「はい」とマイネは小さな声で答えた。 マイネは身体の位置を調整し、それが自分の秘所に丁度合うようにした。更に装備がせり上がってくると、それはまるで愛する男そのものでるかのようにマイネの大切な部分にピッタリと収まっていった。 それにつれて、マイネの身体に快感が走った。もし、これがそれだけの代物なら、紛れもなくマイネは道具を使ったオナニーショウを整備員達に見せつける淫らなハイプそのものだ。 「インターフェース、起動よろしい?」整備員が囁いた。 「いつでもどうぞ」とマイネは答えた。 次の瞬間、マイネが知覚する「身体」の範囲がザッと広がった。この戦闘機そのものがマイネの身体だ。エンジンは足であり、センサーウィングは腕であり、機体下部のエネルギーカノンはパンチを叩き込む拳そのものだ。 ハイプにとって、もっと大量の情報を扱える接点、つまり最も感じる場所を、戦闘機とのインターフェースに使うという発想は極めて合理的だ。この仕組みのおかげで、ハイプそのものにインターフェースのための大改修を行う必要が回避されたとされる。しかし、ハイプが戦闘機と愛し合うという構図は、ある種のフェチズムをかきたてる光景であり、希代のスケベオヤジとして知られるドクター・キガクがフェチズムの美学に沿って設計したという説も捨てきれない。 だが、それは今は重要なことではない。 「シート定位置に上げます」とマイネは宣言した。 整備員が下がると、マイネは身体の芯を経由したインターフェースを通して、シートを引き上げる指示を機体に出した。これで、シートは機体前方を向く。つまり、機体は垂直に立っているので、マイネの背中は床と水平になり、マイネの目は天井を見る姿勢になる。 マイネはマイクに向かって告げた。 「PP-D3艦載機コントロール、こちら高機動MARK-Iファイター実験機。トライアル準備完了。いつでも行けます」 計器をチェックする必要はなかった。全てがグリーンであることは、全てインターフェースを通じて把握していた。 デストロイヤーの艦載機を管制するコントロールが応答した。 「オオハラ中佐機の準備がまだだ。少し待て」 そこに通信が割り込んだ。「こちらMARK-IVのオオハラ中佐。こっちも準備良いぞ」 「了解。エアを抜くぞ、総員格納庫から待避」後半は、格納庫内のスピーカーでも流されていた。 整備員達が待避すると、格納庫の暖色系の照明は寒色系の照明に切り替えられた。 外部気圧が下がっていくのが、まるで自分の皮膚が冷えていくかのようにマイネには解った。 そして、正面つまり天井の扉がゆっくり開き、全開になった。背後では、床の扉も全開になっている。加速噴射で床を痛めないためだ。 「こちらPP-D3艦載機コントロール。こちらの合図で両機とも同時に発進。最初だから好きにやってくれ。自動ジャッジが、どちらかの機体に撃墜判定を出したらそこで終了だ。機体をチェックするために、一度戻ってもらう。OKか?」 「オオハラ了解」 「マイネ、了解です」 「では、カウントダウンする。5,4,3」 マイネは身体を緊張させた。それは身体の内部に入り込んだインターフェースを締め付けて交換される情報量を増大させると同時に、生々しい快楽ももたらした。 「2,1,スタート!」 マイネは強く足をけり込む気分で主エンジンを噴射させた。 すぐに機体は格納庫を飛び出し、星の海に飛び出した。 マイネの背中はシートに押しつけられて動かすのがとても困難だった。だが、顔を動かすことはできた。上を見ると、同じベクトルでMARK-VIが飛んでいる。背後を見ると、今自分たちが飛び出したデストロイヤーが見えたが、あまりにも小さかった。 まあいい。今の状況では、小さい方が良いのだ。 本来このトライアルのベースとなっているのは、実験艦隊(エクスペリメント・フリート)のバトルクルーザー「フィラデルフィア」なのだが、全長2キロメートルもある大型艦では、マイネが機体を制御できなくなって機体を暴走させたとき、激突する危険が大きいと判断されたのだ。そこで、全長がたかが100メートルに過ぎない「フィラデルフィア」搭載デストロイヤー3号機(PP-D3)をベースとして、最初のトライアルを行っているのだ。 うん、大丈夫。あれだけ小さければ、ミスっても激突する危険は少ない。マイネはそう思った。それによって、肩の荷が1つ下りたような気がした。 「そろそろいいかな、お嬢さん」とオオハラ中佐の声が聞こえた。 「どうぞ」とマイネは答えた。 次の瞬間、オオハラ機が消えた。 (後編へ続く) (遠野秋彦・作 ©2006 TOHNO, Akihiko) オルランドの全てが読めるお買い得電子書籍はこれ! 超兵器が宇宙を切り裂き、美女が濡れる。  全艦出撃! 大宇宙の守護者: オルランド・スペース・シリーズ合本
全艦出撃! 大宇宙の守護者: オルランド・スペース・シリーズ合本
|
|
||
|
|